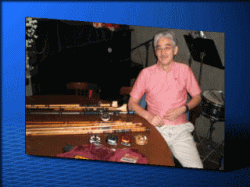
ベストの中身

竿について

リールについて

|
 |
竿は和竿カーボンと使い分けています。
和竿に対しての思い入れは強く、堤防に和竿片手で黒鯛とのやり取りを行う時こそ関東のヘチ釣りを実感できる瞬間であると思います。
ただし近年ではカーボン竿も非常に制度が上がり、和竿に引けをとらない良さが日々改良されています。
|
 |
奥側がカーボン竿 手前が和竿
カーボンは基本的には2・7m〜3mを中心に使用しています。
和竿は8尺〜9尺を中心に使用します。(1尺=約30.3cm)
堤防や状況に合わせて竿の選択していきます。
|
 |
和竿の利点は魚が暴れない事です。
竿の良さは当然軽量化やフィーリングもありますが、魚がかかってからどれだけスムースにやり取り出来るかにかかってると考えます。
その中でも和竿は抜群の吸収力で魚を浮上させます。なんといっても和竿で黒鯛を釣る醍醐味は格別です。
竹は1本1本の性質が異なっており良質な竹ほど価格が上がります。 |
 |
構えた時のフィーリングが重要です。
自分の肘から腕に合わせた長さを選ぶ事も重要です。
魚がかかった瞬間は竿をあまり立てないで魚の動きを止めます。
この時のやり取りは片腕でのやり取りになりますので、黒鯛の強烈な引きをしっかり受け止められるようなイメージをします。 |
 |
印籠部分
通常は矢竹を使用しますが左の竿はカーボンに改良したものです。これにより竹の膨張を防ぎスムースに繋ぐことが出来ます。
|
 |
根彫り淡竹
この形も竹によって違っており非常に味があります。
現在では中々良い形の根彫り淡竹が少なく、左の写真は良質の竹です。 |
 |
リールシートから根付にかけて
今までの経験上から梃子の原理を考えて、太めの竹を使用し、長めに取っています。 |
 |
竹の性質をつかむ
全竹竿は釣行を重ねていく上で、どうしても穂先部に若干のくせが入ってしまいます。これを自分でも小まめにチェックする事が重要です。 |
 |
竿の重さ
カーボンと比べると和竿はどうしても重くなります。ただしバランスが良い和竿では長時間の釣行でもストレスを感じにくくなるものです。 |
 |
和竿のメンテナンス
和竿は生きているものと考えてください。
湿気があるところに放っておくと、性質が変わる事があります。印籠が入らなくなる事もあります。
気を使い保管をします。
和竿は水で丸洗いする事が出来ません。
したがって潮風や塩水をあびたら軽く塗らしたタオルで拭き取り、乾いたタオルで竿油を塗っておきます。
長持ちの秘訣です。 |
 |
和竿の補修と改良
基本的には自分で行わないほうがいいと思います。購入した竿師に見てもらう事をお奨します。 |
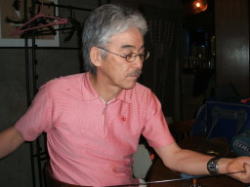 |
穂先に関して
黒鯛を見るとわかるようにほとんどが歯です。
聞いたとき、合わせを入れたときに餌を離してしまってはもったいないです。固すぎず、柔らかすぎずが大切です。 |
 |
全竹竿の中通し竿
全竹竿で中通し竿を作成するには、かなりの技術が要求されます。完成されたものは本当に圧巻です。
抜群のタメで魚も無理なくあがってきます。また風が吹いても穂先に糸が絡みません。 |
 |
穂先のみカーボンの中通し竿
竹の良さとカーボンの強さを融合させた竿
穂先への癖も入りにくく絶品です。
|
 |
竿選び
あんまり竿をころころ変えるのもよくないと思います。
この釣りをこれから始める方は1本の竿を信じて使い続ける事もひとつの上達への方法だと思います。 |
 |
最後に・・・
竿はこの釣りで非常に重要なものです。
しかし、人がいいとしている竿も自分で使ってみなくてはわかりません。人それぞれ合わせのタイミングややり取りの癖や骨格が違うように自分に合わせた竿に出会う事が重要です。 |